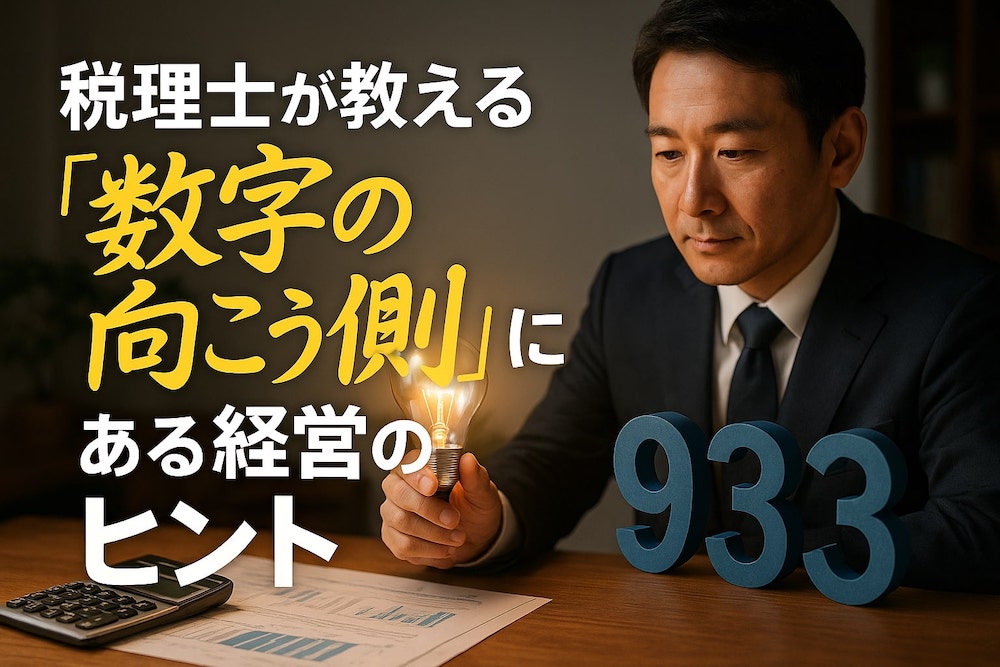東京の下町にある小さな事務所で、私がよく耳にする言葉があります。
「決算書は良いのに、なぜか資金繰りが苦しい」
「売上は伸びているのに、利益が出ない」
「数字からは何も問題が見えないのに、社内のモチベーションが下がっている」
これらは、いずれも経営の現場で感じる「数字と現実のズレ」を表しています。
財務諸表は企業の健康診断書のようなものです。
しかし、健康診断の数値が正常でも、体の不調を感じることがあるように、企業経営においても数字だけでは見えない現実があります。
私は30年以上、税理士として多くの中小企業の財務を見てきました。
その経験から言えるのは、真の経営改善は「数字の向こう側」にある人間の事情や思いを理解することから始まるということです。
本記事では、財務諸表の数字を単なる羅列ではなく、生きた情報として読み解くヒントをお伝えします。
数字が語りかけてくること
財務諸表の読み方に”人間味”を加える
財務諸表は、企業活動を数字に置き換えたストーリーです。
ただ眺めるだけでは、そこに登場する「人」の存在が見えてきません。
例えば、ある製造業の決算書に目を通した時のことです。
売上原価率が前年より5%上昇していました。
一般的な分析では「原材料の高騰か、製造効率の低下だろう」と結論づけるところです。
しかし現場を訪れてみると、ベテラン職人が3名退職した後、新人が入ったことで品質維持のために検品を厳格化していたことがわかりました。
数字の裏には、技術伝承の課題という「人の物語」が隠れていたのです。
財務諸表を読む際は、まず素直に数字を受け止めてください。
その上で「この数字は誰のどんな行動や判断から生まれたのか」と考えることで、単なる数値分析を超えた理解が生まれます。
売上・利益だけでは測れない健全経営
「増収増益」という言葉は、経営の成功を示す最も簡潔な表現です。
確かに売上と利益は企業活動の重要な成果ですが、それだけで経営の健全性を判断できるでしょうか。
私が担当する老舗の和菓子店は、コロナ禍で大きく売上を落としました。
しかし経営者は固定費を徹底的に見直し、在庫管理を精緻化することで驚くほど強靭なキャッシュフロー体質を築き上げました。
売上減でも、手元資金は着実に増えています。
健全な経営とは、売上や利益の絶対額ではなく、いかに安定したキャッシュを生み出せるかにあります。
キャッシュフロー計算書を読む際には、特に営業活動によるキャッシュフローに注目してください。
これが継続的にプラスであれば、本業の収益力は健全と言えます。
さらに投資活動と財務活動のバランスにも目を向けましょう。
営業キャッシュフローがプラスでも、過剰な投資や借入返済に資金が流れていると、将来の資金繰りが厳しくなる可能性があります。
異常値の裏にある”現場の声”をどう拾うか
決算書や月次試算表には、時として「異常値」が現れます。
前月比200%の売上増加や、急激な経費の増加など、通常とは異なる動きを示す数字です。
こうした異常値は、単なる会計上の問題ではなく、現場の重要なシグナルであることが多いのです。
あるIT企業では、外注費が突如3倍に膨れ上がりました。
数字だけ見れば「コスト管理の失敗」と判断されかねません。
しかし話を聞くと、有能なエンジニアの退職を補うために、急遽外部リソースを調達したことが原因でした。
この「異常値」は、実は人材育成と定着に課題があることを示していたのです。
異常値を見つけたら、まず「なぜこの数字が生まれたのか」と現場に問いかけてみてください。
そこから浮かび上がる本質的な課題こそ、経営改善の糸口となります。
経営者が陥りがちな「数字の落とし穴」
「利益が出ている=安心」の思い込み
「今期も黒字だから大丈夫」
多くの経営者がこの思い込みで経営判断を誤ります。
利益が出ていても、実は様々なリスクが潜んでいることがあるのです。
ある建設会社では5年連続で増収増益を達成していました。
しかし内訳を見ると、利益の90%が特定の大口顧客からの案件に依存していたのです。
この状況は「見かけの好調」に過ぎず、大口顧客の方針転換という予期せぬ出来事で経営危機に陥る可能性をはらんでいました。
安定した経営のためには、利益の「質」や「持続可能性」を常に意識する必要があります。
特定の商品や顧客への依存度、利益を生み出す事業の将来性、業界全体の動向など、数字の向こう側にある事業の本質を見つめることが重要です。
節税ばかりに目を奪われるリスク
税理士として最も多く相談されるのが「節税」です。
もちろん適正な節税は企業の義務でもあります。
しかし「節税」という言葉に魅力を感じるあまり、本来あるべき事業投資や人材育成を犠牲にするケースを少なからず見てきました。
例えば、期末に急いで設備投資をして減価償却費を計上し、課税所得を圧縮するという方法があります。
確かに短期的な税負担は軽減できますが、本当に必要な設備なのか、投資効果はあるのかといった検討が疎かになりがちです。
真の経営改善は、「税金をいかに減らすか」ではなく「いかに本業で儲けるか」という視点から始まります。
税金は利益の結果生じるものであり、利益を生み出す力を強化することこそが本質です。
「今、会社に最も必要な投資は何か」を常に考え、その上で最適な税務戦略を立てるという順序を守りましょう。
キャッシュフローを”感覚”で理解する重要性
損益計算書の「利益」と実際の「現金」は別物です。
この基本的な事実を体感的に理解している経営者は意外と少ないものです。
ある飲食店チェーンの社長は、毎月の試算表で利益が出ていることを確認し、新規出店を次々と決定していました。
しかし、売掛金の回収遅れや新店の初期投資が重なり、ある月突然資金ショートに陥ったのです。
「利益」は発生主義で計上される会計上の概念ですが、支払いは現金で行われます。
この違いを感覚的に理解するには、日々の経営判断の中で常にキャッシュの動きを意識することが欠かせません。
例えば「この契約で利益はいくら出るか」だけでなく、「いつ入金されるか」「支払いはいつ発生するか」という視点で考える習慣をつけましょう。
特に成長期の企業は、資金繰り表を毎月更新し、3か月先までの現金の流れを常に把握しておくことをお勧めします。
税理士が見た中小企業のリアル
小さな商店から学んだ”継続の知恵”
私の顧問先に、創業100年を超える老舗の文具店があります。
大型チェーン店の進出やネット通販の台頭で、業界環境は厳しさを増す一方です。
それでも安定した経営を続けられている理由は何か。
その秘密は、財務諸表には直接現れない「非財務情報」にありました。
この店の強みは、地域の学校や企業との深い信頼関係です。
売上台帳を見ると、単価は大手より高いにも関わらず、40年以上取引を続ける顧客が少なくありません。
棚卸資産回転率は業界平均の2倍で、無駄な在庫を持たないきめ細かな発注管理を行っています。
さらに、家賃や人件費などの固定費を最適化し、景気に左右されにくい筋肉質な経営体質を維持しているのです。
大切なのは「今日より明日、明日より明後日と少しずつ良くしていく」という継続の姿勢です。
派手な成長戦略より、日々の小さな改善の積み重ねが100年企業を作るのだと、この文具店から学びました。
事業承継の現場で見えた「数字に現れない不安」
中小企業庁の調査によると、2025年までに70歳を超える中小企業の経営者は約245万人に達し、そのうち約半数が後継者未定とされています。
事業承継は今や中小企業の最重要課題となっていますが、その難しさは財務諸表の数字だけでは理解できません。
私が関わった金属加工会社の事例では、表面上は健全な財務状態でした。
自己資本比率40%、営業利益率8%と業界平均を上回る好業績です。
しかし承継を進めるにつれ、数字には表れない様々な課題が浮かび上がりました。
創業者の個人信用で成り立っていた取引関係、属人化した技術やノウハウ、従業員との人間関係など、「見えない資産」の承継が最大の壁だったのです。
事業承継の準備は早ければ早いほど良いと言われますが、それは単に株式の移転や税金対策だけの話ではありません。
後継者が「見えない資産」を理解し、自分のものにするための時間が必要なのです。
事業承継を検討している経営者の方は、財務諸表の整理と同時に、「自社の強みは何か」「それは誰が担っているのか」という非財務情報の整理も進めていくことをお勧めします。
相談が早ければ防げた”ある倒産”の話
私が経験した最も残念なケースは、創業30年の印刷会社の倒産です。
月商1,500万円、従業員15名の会社でした。
倒産の3か月前、初めて相談を受けた時には既に手遅れの状態でした。
借入金の返済が滞り、仕入先への支払いも遅延し始めていたのです。
財務諸表を分析すると、実は3年前から危険信号は出ていました。
売上高は横ばいだったものの、売上総利益率が徐々に低下し、最後の1年で5ポイント下落していたのです。
原因を探ると、デジタル化の波に乗り遅れ、価格競争に巻き込まれていたこと、そして設備投資のための借入金の返済負担が重くのしかかっていたことがわかりました。
もし2年前の段階で相談があれば、事業転換や財務体質の改善など、様々な手を打つことができたはずです。
企業経営において、「相談するのは恥ずかしい」という感覚を捨てることが重要です。
問題が小さいうちに専門家に相談することで、選択肢は広がります。
特に資金繰りの悪化は、進行が速く取り返しがつかなくなりやすいため、早期の対応が不可欠です。
毎月の試算表で売上総利益率や経常利益率が継続的に低下している場合は、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
「数字の向こう側」に目を向ける習慣
会計ソフトに頼りすぎない「見る力」の育て方
現代の経営者は恵まれています。
クラウド会計ソフトの普及により、リアルタイムで財務状況を把握できるようになりました。
しかし、便利さの反面、「会計ソフトを見ているから大丈夫」という過信が生まれていることも事実です。
会計ソフトは数字を整理してくれますが、その意味を解釈し、経営判断に結びつけるのは人間の仕事です。
数字を「見る力」を育てるためには、まず財務諸表の構造を理解することが基本です。
その上で、以下の習慣を身につけることをお勧めします。
1. 毎月同じ指標を継続的に追う
- 売上総利益率
- 経常利益率
- キャッシュコンバージョンサイクル(売上債権回転日数+棚卸資産回転日数-仕入債務回転日数)
2. 数字と現場をリンクして考える
- 「この数字が変化したとき、現場では何が起きていたか」を振り返る
- 逆に「現場のこの変化は、どの数字に影響するか」を予測する
3. 業界標準や競合と比較する
- 同業他社の財務指標と自社を比較する(金融機関経由で入手可能)
- 業界平均との乖離がある場合、その理由を考える
これらの習慣を通じて、数字の意味するところを直感的に理解できるようになります。
会計ソフトは道具であり、それを使いこなすのは経営者自身なのです。
経営会議に”問い”を持ち込む技術
経営会議の場では、しばしば「先月の売上は目標比98%」「経費は予算内に収まっている」といった報告で終わってしまいがちです。
しかし真の経営改善は、数字の先にある「なぜ」を問うことから始まります。
効果的な経営会議のために、財務数値から派生する「問い」を準備しておくことをお勧めします。
例えば、売上が目標に届かなかった場合:
- 「どの商品・サービスが特に不振だったのか」
- 「顧客セグメント別に見ると、どこに変化があったのか」
- 「競合の動向に変化はなかったか」
原価率が上昇した場合:
- 「どの原材料・工程でコスト増が発生しているのか」
- 「一時的な要因か、構造的な問題か」
- 「価格転嫁の余地はあるか」
このような問いを通じて、数字から実態へと議論を深めていくことが重要です。
またこうした問いは、単に原因を追及するためではなく、「次に何をすべきか」という行動につなげるために行うことを忘れないでください。
問題の原因が明らかになったら、すぐに対策を検討し、責任者と期限を決めて実行に移すというサイクルを回すことで、経営会議は単なる報告の場から改善の原動力へと変わります。
「この数字、誰のため?」と問い直す視点
財務諸表の数字は、様々な利害関係者に対して異なる意味を持ちます。
銀行は返済能力を示す指標に、投資家は成長性に、従業員は安定性に、それぞれ注目するでしょう。
そして時に、それらの期待に応えようとするあまり、本来あるべき経営の姿を見失うことがあります。
例えば、銀行対策のために無理な利益計上をしたり、投資家向けに過度な成長戦略を打ち出したりすることは、長期的には企業の健全性を損ないかねません。
財務指標を見るとき、常に「この数字は誰のためのものか」と問い直す習慣をつけることが大切です。
そして最終的には「持続可能な経営のために、本当はどうあるべきか」という視点で判断することが重要です。
特に中小企業においては、短期的な数字の変動に一喜一憂するのではなく、5年、10年先を見据えた経営判断が求められます。
「この判断は10年後の会社にとって良いことか」という問いを持つことで、数字に振り回されない経営が可能になるのです。
今日からできる、小さな経営改善アクション
週1回、数字と向き合う”10分ミーティング”
経営改善の第一歩は、現状を正確に把握することです。
しかし多忙な経営者にとって、毎日財務状況をチェックするのは現実的ではありません。
そこでお勧めしたいのが、週に1回、たった10分だけ数字と向き合う習慣です。
以下は、効果的な「10分ミーティング」の進め方です。
1. 見る力を育てる
- 毎週月曜日の朝一番など、固定した時間を設定する
- 売上・売掛金残高・買掛金残高・預金残高の4つだけに集中する
- 前週比・前月同期比・前年同期比の変化率をチェックする
2. 問いを立てる
- 数字に大きな変動があれば「なぜそうなったのか」と問う
- 問題点があれば、担当者に確認する事項をメモする
3. 行動につなげる
- 次の1週間で取り組むべきアクションを1〜2つ決める
- 翌週のミーティングで、そのアクションの結果を確認する
この10分ミーティングを継続することで、財務状況への感度が高まり、問題の早期発見・早期対応が可能になります。
特に資金繰りに関わる預金残高と売掛・買掛金の推移は、企業の生命線とも言える指標です。
これらを継続的に追うことで、黄信号が灯った段階で対策を講じることができるようになります。
家計簿感覚で始めるキャッシュ管理
企業経営と家計には共通点があります。
どちらも収入と支出のバランスが取れていなければ、長期的な安定は望めません。
特に中小企業では、経営者自身が「家計簿感覚」でキャッシュを管理することが有効です。
以下は、家計簿の知恵を活かしたキャッシュ管理のポイントです。
1. 「財布分け」の発想を取り入れる
- 日常の運転資金、納税資金、設備投資資金など、目的別に口座を分ける
- 売上が入ったら、あらかじめ決めた割合で各口座に振り分ける
2. 「見える化」でムダを削減する
- キャッシュの出入りを項目別にグラフ化し、推移を見える化する
- 「この支出は本当に必要か」と定期的に見直す機会を設ける
3. 「先取り貯蓄」の考え方を応用する
- 将来の設備投資や納税に備え、毎月一定額を積み立てる
- 突発的な出費に備え、売上の5%程度を「予備費」として確保する
複雑な財務モデルよりも、このような直感的なキャッシュ管理の方が、中小企業では実行力が高まることが多いと感じています。
経営は難しく考えすぎず、「入ってくるお金」と「出ていくお金」のバランスを取ることから始めましょう。
その上で、よりキャッシュを生み出せる事業構造に変えていくことが、長期的な経営安定につながります。
税理士との対話を”経営の棚卸し”に活かす方法
多くの経営者は、税理士との面談を「税金の相談」「決算の報告」の場と考えています。
しかし税理士は、あなたの会社の財務状況を最も詳しく知る専門家の一人です。
この関係を、単なる税務顧問としてではなく、経営改善のパートナーとして活用することをお勧めします。
1. 税理士面談の前に準備すること
- 直近の業績について、自分なりの分析と課題を整理する
- 経営上の悩みや将来の構想を箇条書きにしておく
- 「この数字はどう解釈すべきか」という具体的な質問を用意する
2. 面談中に心がけること
- 税金の話だけでなく、経営全般についての見解を求める
- 「同業他社と比べてどうか」という視点での意見を聞く
- 決算書の数字から見える強みと弱みを整理してもらう
3. 面談後のアクション
- 税理士からの助言を経営会議で共有する
- 指摘された課題について、具体的な改善計画を立てる
- 次回面談までの進捗状況を記録しておく
税理士との対話は、第三者の目で自社を見つめ直す貴重な機会です。
「税務処理」という枠を超えて、経営全般についての対話を深めることで、新たな気づきが生まれるはずです。
また年に一度は、税理士を交えた「経営計画の見直し会議」を開くことも効果的です。
特に経営改善に積極的に取り組みたい企業には、神戸で税理士との連携を重視している濱田会計事務所のような、経営者との密なコミュニケーションを大切にする事務所がおすすめです。
中期的な視点で財務体質の改善に取り組むことで、企業の持続的な成長につながるでしょう。
まとめ
財務諸表の数字は、企業活動の結果を映し出す鏡です。
しかし鏡に映るのは表面的な姿だけであり、その奥にある「人の思い」「現場の実態」「未来への可能性」は、数字だけでは捉えきれません。
本当の経営改善は、数字を「読む」だけでなく、その向こう側にある物語を「聴く」ことから始まります。
私は30年以上、税理士として多くの中小企業の歩みに寄り添ってきました。
その経験から言えるのは、最も成功している経営者は、数字を冷静に分析する力と、人の気持ちに共感する温かさを併せ持っているということです。
財務諸表は難解な暗号ではありません。
それは、あなたと従業員、取引先、お客様との関係性を映し出す物語です。
その物語に耳を傾け、明日への一歩を踏み出すお手伝いができれば、税理士冥利に尽きると感じています。
あなたの数字には、あなた自身の物語があります。
その物語を大切に紡ぎながら、持続可能な経営を実現していきましょう。
最終更新日 2025年12月17日 by matsuu